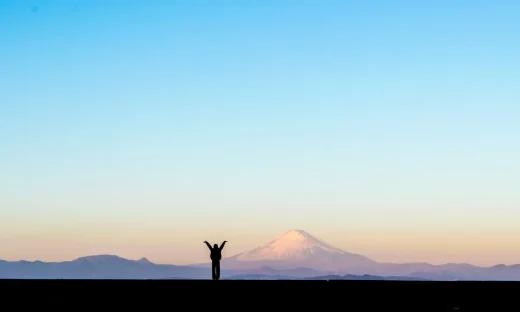非エンジニアの現場視点を活かす開発設計とは?業務システムの「ユーザー起点設計」入門

近年のシステム開発では、要件定義や運用フェーズにおいて、非エンジニアの参加がますます重要になっています。 とくに業務システムの開発では、実際にシステムを使うのはエンジニアではなく、現場のスタッフや部門の担当者たちです。
この記事では、「システム開発会社や受託開発企業を検討している担当者」に向けて、非エンジニアの現場知見を設計フェーズに組み込むための考え方と方法論を、実務的に解説します。
なぜ「非エンジニア視点」の設計が求められているのか
従来の開発体制では、要件定義をエンジニアがまとめ、現場からは要望を文書化して伝える、という分業スタイルが一般的でした。 しかしこの方法では、以下のような課題が多く発生します。
・現場の本質的なニーズが仕様に落ちない
・開発完了後、「使いにくい」「結局Excelのほうが早い」となる
・属人化したExcel業務が再び台頭する
この背景には、「設計段階でのコミュニケーションの断絶」があります。 エンジニアと現場担当者が同じ言葉で会話できず、共通認識が形成されないままプロジェクトが進むことは、開発失敗の主要因のひとつです。
その断絶を埋めるために、「現場ユーザーが直接参加できる設計プロセス」が今、注目されています。 現場の知見が早期に設計へ反映されることで、仕様と業務が自然と一致しやすくなり、開発の手戻りや運用段階での「使われないシステム」の発生を防ぎます。
現場の声をどう取り込むか:具体的なプロセス設計
「参加設計型システム開発」を進めるには、下記のステップを明確に設計する必要があります。
1. プロトタイピングツールによる共通認識の可視化
FigmaやAdobe XDなどのUIツールを活用し、「実際の画面に近い構成」で操作フローを共有します。これにより、現場担当者が口頭で説明できないニーズや操作感を視覚的に表現することが可能になります。
また、操作手順に関する誤解を防ぐだけでなく、開発チームにとっては画面遷移の設計精度を高めることにも繋がり、双方にとってメリットがあります。
2. 現場参加者による「業務シナリオベース」レビュー
単なる仕様チェックではなく、現場担当者が日常業務の流れに即して「業務シナリオ」を読み上げながら確認するスタイルを採用します。
例えば「午前9時、来客受付があった後に伝票登録をし、そのデータを経理に連携する」といった具体的な業務の一連の流れをベースに、UIや機能が整合しているかどうかをレビューします。
この方法により、机上での想定では見落とされるような業務上の分岐や例外パターンを発見しやすくなります。
3. 言語の壁を超える「操作可能モック」の活用
ノーコード・ローコードツール(Retool、OutSystems、Budibaseなど)を活用し、「ほぼ実働に近い操作画面」を仮作成してフィードバックを得ます。
特に非エンジニアの参加者にとっては、画面の見た目と操作感を通じて「直感的な理解」が可能になるため、具体的な要望や改善提案が生まれやすくなります。
実装フェーズにおける「現場巻き込み設計」の工夫
設計だけでなく、実装段階でも現場のフィードバックを素早く取り込む体制が求められます。特に以下のような取り組みが有効です。
デモ会の定例化とUIフィードバック収集
週1回程度のスプリントデモとUIレビューを習慣化し、フィードバックを「システム設計の構成要素」として明文化します。
定例化することで「使い勝手に関する声が上がる場」が確保され、設計変更や改善ポイントが早期に特定できます。また、開発側と現場側の信頼関係構築にも寄与します。
管理画面やワークフローの設定権限を現場に
ユーザー自身が「設定変更」や「テンプレート編集」などを行えるよう、権限設計も合わせて見直す必要があります。
現場が自律的に調整可能なシステムは、運用時の柔軟性が高く、長期的に見ても改善要望への対応スピードが上がります。属人化の回避や運用コストの削減にもつながります。
非エンジニア向けUI/UX設計で押さえるべき視点
情報量が多い業務システムでは、「使いやすいUI」は単に見た目の問題ではありません。実用的な導線設計や認知負荷の軽減が求められます。
・用語は「業務言語」で統一(例:「インシデント」ではなく「報告内容」)
・操作ボタンは目的別に配置(例:「保存」「報告」「一時保存」)
・リストや選択肢は利用頻度順に表示
・必須項目を色や記号だけに依存せず、文言で強調する
さらに、ユーザーにエラーが発生した際のリカバリー動線(例:未入力の自動スクロール、ガイドテキストの常時表示)を用意することで、「業務中断」を防ぐUXの構築が可能になります。
まとめ:エンジニア主導から「ユーザー共創」へ
業務システム開発において、「非エンジニアは仕様の受け手」という考え方はすでに時代遅れになりつつあります。 ユーザー自身が開発初期から関与し、業務フローに沿った仕様を共に考える体制が、「使われるシステム」を作るために不可欠です。
受託開発会社としても、要件定義フェーズで「現場参加型プロセス」の提案ができるかどうかが、競争力の差となっていくでしょう。 技術力だけではなく、いかに「ユーザーと並走できるか」が、これからの開発成功の鍵を握るといえます。