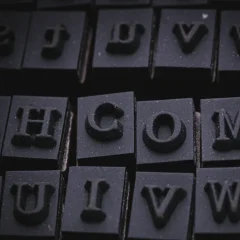小規模チームで始める「段階的モジュール設計」入門:中長期運用を見据えたシステム構築の勘所
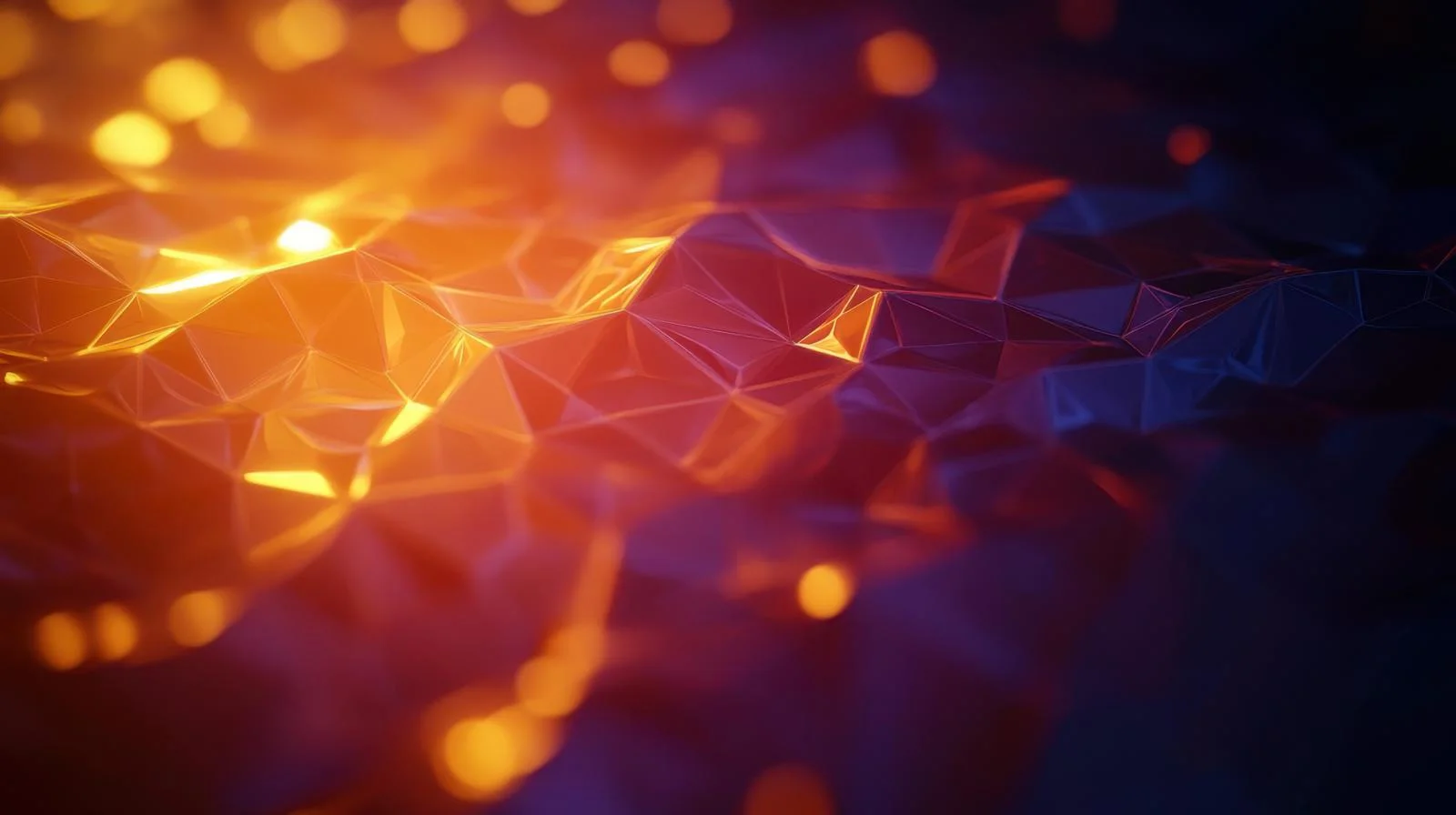
はじめに:なぜ今「段階的モジュール設計」が必要か
システム開発の初期段階では、ビジネス要件のスピード実現が最優先されることが多く、「まずは動くものを作る」という判断が合理的に見える場面も少なくありません。しかし、初期開発で拙速に構築されたアーキテクチャは、リリース後に新機能の追加や仕様変更が重なっていくにつれ、次第に「技術的負債」として運用・保守の足かせになります。
特にスタートアップや中小企業のように限られた人員と予算の中で持続的に開発を進めていく場合、初期の段階から「将来的な構造拡張の見通し」を組み込んでおくことが重要です。その答えとして有効なのが、「段階的モジュール設計」という考え方です。
この記事では、Webシステム開発や業務アプリ開発を外注しようとしている企業担当者に向けて、スモールスタートかつ拡張可能な設計戦略としての「段階的モジュール設計」の実践的な進め方を解説します。
モノリシックとマイクロサービスの二極構造を超えて
モノリス構成の利点と限界
初期開発フェーズでは、チーム規模や開発期間に対する最適解としてモノリシック(単一構造)なアーキテクチャが選ばれやすいです。実際、以下のような利点があります。
- コードが一箇所に集約され、実装スピードが速い
- テスト・ビルド・デプロイのフローが単純
- 開発者同士の連携が密になりやすい
一方で、以下のような構造的限界にも早期に直面します。
- 機能が増えると1つのコードベースに責務が集中して可読性が低下
- 小さな改修でも全体を意識しなければならずデグレが多発
- 人数が増えたときの役割分担が曖昧化
フルマイクロサービスの落とし穴
マイクロサービスは構造的な疎結合を実現できる強力なアプローチですが、その導入には高度な運用体制が必要です。
- 各サービスごとにデプロイ・監視体制を構築しなければならない
- 認証やロギング、モニタリングの仕組みを共通化する必要がある
- 通信失敗やサービス間連携の整合性検証が難しい
初期開発においては「そこまでの分散管理が必要なのか?」という問いが生まれるのも事実です。
ハイブリッド戦略としての「段階的モジュール設計」
そこで登場するのが、「段階的モジュール設計」という思想です。これは、最初はモノリス的に構築しながら、内部構造では明確な責務分離と将来的な分割しやすさを担保する設計手法です。初期フェーズでは開発効率を確保しつつ、将来的なスケールに備える“中庸”のアーキテクチャ戦略です。
段階的モジュール設計を進める具体ステップ
ステップ1:ドメイン単位の機能分離と名前空間管理
まずは業務領域ごとにコードを整理します。典型的なドメインには以下のようなものがあります:
- ユーザー認証・管理
- 商品やサービスの管理
- 決済・請求処理
- 通知・アラート制御
これらを別々のディレクトリ、サービスクラス、ルーティング定義、APIコントローラーに分離するだけで、構造の見通しが一気によくなります。
ステップ2:ドメイン間の依存方向を制御する
ドメイン同士の関係性が複雑になると保守性が損なわれます。以下のルールを導入することで依存の階層を整理できます。
- 下位レイヤー(ユーティリティやDBアクセス層)は上位からのみ参照可能
- 共通機能(ログ出力、ファイルアップロードなど)は一方向依存
- インターフェースを導入して依存関係を抽象化
ステップ3:UIレイヤーとアプリケーションロジックの分離
フロントエンドから見れば、どんなに綺麗なAPIでも一体化されたコードは変更が困難です。API設計やBFF(Backend for Frontend)などの導入により、UI/UXと業務ロジックの独立性を高めることが推奨されます。
ステップ4:デプロイやテスト単位のモジュール分割へ移行
プロジェクトが進行し、複数メンバーやチームが関与するようになった段階で、モジュール単位のビルド・デプロイや単体テストの分離が求められます。コードベースの構造が整っていれば、機能単位でのCI/CDの導入も円滑になります。
設計原則として導入すべき「契約と責務」の意識
「責務を定義する」ことの重要性
各モジュールに「何をしてよいか」「何をしてはいけないか」を明示し、それを構成ドキュメントに残す文化が必要です。責務を曖昧にしたままモジュールを分けても、依存関係の混乱は解消されません。
インターフェース契約の明確化
REST API、GraphQL、gRPCなど、サービス間インターフェースの仕様は、OpenAPIやProtocol Buffersといった仕様書により明示的に契約として定義することが重要です。これにより、開発者間での認識齟齬が減り、テストや改修のスムーズさが向上します。
依頼側が意識すべき「設計を共有するための観点」
発注者が設計思想に関与できるかどうかは、プロジェクト成功の鍵を握ります。以下のような観点で開発会社と設計議論をすることが推奨されます。
- システムは将来的にどこまで拡張する可能性があるか
- 一時的な社内業務アプリか、外販・他拠点展開を見据えたものか
- API公開や外部連携の有無
- コンポーネントの再利用性を重視する必要があるか
これらを早期に提示することで、開発パートナー側も「目の前の要件をこなす」だけでなく、「将来に備える設計」に対して納得感のある設計提案が可能になります。
まとめ:「設計」は初期開発の技術投資である
段階的モジュール設計は、目の前の要件だけでなく、将来の変化にも耐え得る設計方針を意識したアーキテクチャ戦略です。初期フェーズでは見えにくい価値かもしれませんが、数年後の拡張・改修・連携といったフェーズにおいて、圧倒的な効果を発揮します。
発注側企業としても、こうした設計方針を理解し、仕様書や画面の裏側にある「構造」に対して関心を持つことが、優れた開発パートナーとの関係構築や中長期的なコスト削減に直結します。
段階的に育てていけるシステム。それを可能にするための設計思想が、「段階的モジュール設計」なのです。