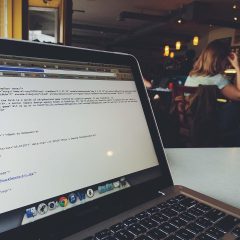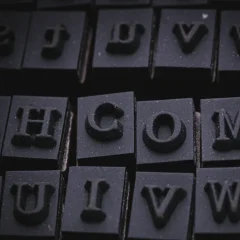「社内ユーザーごとの操作アシスト導入プロジェクト」|業務システムに“使い方”を組み込むという発想

業務システムやWebシステムの開発依頼において、多くの企業が注目するのは「機能要件」や「システム設計」です。しかし、実際に運用が始まってから浮上する課題の多くは、「システムが使われない」「操作がわかりづらい」「現場に浸透しない」といった“定着率”に関するものです。
このギャップを埋めるソリューションとして、近年注目され始めているのが「ユーザーごとの操作アシスト機能」です。
本記事では、実際の開発ユースケースとして、「社内ユーザーの習熟度・職種ごとに最適化された操作ガイド(アシストUI)」を業務システムに実装し、定着率と業務効率の大幅な改善を実現したプロジェクト事例を紹介します。
システム開発会社の選定や要件定義において見落とされがちな「操作補助」領域を掘り下げ、運用フェーズを見越したシステム導入のヒントをお届けします。
プロジェクトの背景:属人化・問い合わせ増加・操作ミス多発の課題
本プロジェクトは、従業員数200名超の製造業企業において、老朽化した受発注管理システムを刷新するタイミングでスタートしました。導入前の課題として、以下のような状況が浮き彫りになっていました。
-
ベテラン社員しか操作方法を把握しておらず、マニュアルは形骸化
-
毎月の情シス部門への問い合わせが100件を超える
-
新人が誤操作で取引先情報を上書き・削除してしまうリスク
このような問題を解決するために、単にUIを見直すだけではなく、「ユーザーを操作の迷子にさせない設計」が必要だという結論に至り、操作アシスト機能の実装が検討されました。
解決策として選ばれた「ユーザー別操作アシスト」設計とは?
「操作アシスト」とは、画面上に表示されるポップアップ型の説明・ツールチップ・モーダルガイド・タスクリストなどを通じて、ユーザーが今なにをすべきか、どう操作すべきかを誘導する仕組みです。
このプロジェクトでは、以下のような設計方針が採用されました。
ユーザー属性別にアシストの出し分けを行う
-
初回ログイン時は「全操作ガイド付きモード」
-
中堅以上のユーザーには「ツールチップのみの軽量ガイド」
-
管理者やベテラン社員にはアシスト機能非表示
操作フローごとにシナリオ型アシストを用意
-
例:「商品登録 → 価格設定 → 在庫数入力 → 登録確認 → 完了」までを1セットでステップ表示
-
各ステップには簡単な説明・NG例・成功事例を併記
操作ミスが多かった箇所にだけ補助表示を強化
-
過去の操作ログを分析し、頻繁にエラーが起きた画面にだけガイドを追加
-
不要なアシストの多発を防止
技術的な実装:実は特別なフレームワークは不要
このアシストUIはVue.jsとReact.jsどちらでも実装可能で、専用のライブラリ(Intro.js、Shepherd.jsなど)を活用することで実装コストを抑えながら導入できました。
さらに、以下の工夫により拡張性とメンテナンス性を担保:
-
アシスト内容をJSON定義ファイルとして外部化(ノーコード編集可能に)
-
バージョン管理と一緒にアシストガイドも更新できる仕組み
-
ロール設計と紐づいた表示ロジックで属性制御
運用フェーズで得られた効果と数値的インパクト
導入から3ヶ月後、以下のような効果が定量的に確認されました。
-
問い合わせ件数:月間100件 → 月間30件に減少(70%削減)
-
誤操作によるトラブル:ゼロ件に(前年度比)
-
システム利用率(ログイン継続率):初月70% → 3ヶ月後85%に改善
特に新人社員からは「説明書を読まなくても操作できた」「先輩に何度も聞かずに済んだ」と高評価を得ており、定着支援ツールとしての効果が如実に表れました。
発注者視点で学ぶべき導入のポイント
このユースケースから得られる最大の教訓は、「アシスト機能も立派な業務改善設計の一部」という視点です。以下の点を開発依頼時に考慮することで、より“使われるシステム”の実現に近づけます。
-
画面設計の段階で「操作の難所」を洗い出しておく
-
属人化しがちな業務領域にはあえて「冗長なUI補助」を導入する
-
操作ログを残す設計を事前に入れておき、改善対象を可視化
-
将来的にアシスト表示のON/OFFが制御可能であること
操作アシストを活かすための開発会社との連携のあり方
開発会社に操作アシストを依頼する場合、「実装できますか?」という聞き方ではなく、以下のような視点で相談するのがポイントです。
-
「操作ミスや定着率に課題があるが、どんな設計で解決できますか?」
-
「ユーザー属性ごとにUIを変える柔軟性は設計できますか?」
-
「アシスト内容を非エンジニアが編集できる設計は可能ですか?」
これらに対し、仕様書をベースに提案ではなく「業務背景」を踏まえて提案できる会社が、真に信頼できるパートナーです。
まとめ:「操作できる」ではなく「操作しやすい」設計が成果を生む
システム開発において、ユーザーインターフェース(UI)は“最後に考えるもの”とされがちです。しかし、実際に成果を左右するのは、「ユーザーがどれだけ迷わず、正しく、継続的に使えるか」という運用の質です。
今回の事例で採用された操作アシスト機能は、特別な技術でも大規模な予算が必要なわけでもありません。しかし、「使われるシステム」を本気で作ろうとする姿勢と、それを受け止められる開発会社との連携が、最終的な成果を決定づけます。
もしこれから業務システムの開発依頼を検討されているなら、「アシスト設計」という視点を加えることで、費用対効果の高いプロジェクトに進化するはずです。