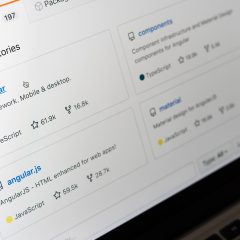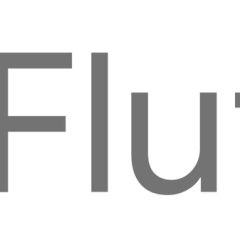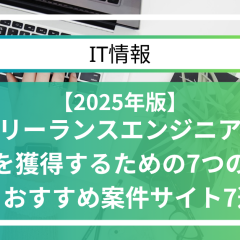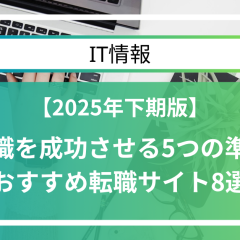エラーメッセージの設計はなぜ重要か?“わかりやすい失敗”がアプリの使いやすさを左右する

システムやアプリケーションを利用する上で、避けて通れないのが「エラー」への対応です。ユーザーが入力ミスをしたり、通信状況が悪化したり、サーバーが一時的に停止していたりと、どんなに丁寧に作られたシステムでも「うまくいかない瞬間」は必ず発生します。
このとき、ユーザーにどう伝えるか──それが「エラーメッセージ設計」の話です。
本記事では、非エンジニアの発注担当者にもわかりやすく、「エラー表示の設計」がなぜ重要で、どのように提案や設計時に評価すべきかを具体的に解説していきます。
よくある課題:ユーザーが「なぜ失敗したか分からない」状態になる
多くのアプリやシステムで、次のような経験をしたことがあるのではないでしょうか。
- 「エラーが発生しました」とだけ表示されて原因も対処法も書かれていない
- 入力フォームでエラーが出ても、どの項目が間違っているのか分からない
- アプリの利用中に処理が止まり、リトライできずに閉じるしかない
このような「分からないエラー表示」は、ユーザーの操作意欲を削ぎ、システムに対する不信感を高めてしまいます。特に非エンジニアの一般ユーザーが対象の場合、エラー設計の質はそのまま「使いやすさ」に直結します。
エラーメッセージの種類と表示ポイントの分類
エラーはシステム内のどこでも発生し得ますが、大きく分けて以下の3つのカテゴリに分類して考えると分かりやすくなります。
1. 入力バリデーションエラー
- ユーザーがフォームに不適切なデータ(空欄、形式ミスなど)を入力した場合に発生
- 表示ポイント:該当の入力欄の近く、もしくはフォーム全体の上部
- メッセージ例:「メールアドレスの形式が正しくありません」
2. 通信・処理系エラー
- サーバーとの通信が失敗、外部APIからエラー応答が返るなどのケース
- 表示ポイント:画面上部のグローバル領域や、画面全体のモーダル表示など
- メッセージ例:「サーバーとの通信に失敗しました。電波状況をご確認ください」
3. 権限・業務ロジックエラー
- 未認証ユーザーがアクセスした、利用期限が切れている、他ユーザーと処理が競合したなど、業務ルールに基づく制御
- 表示ポイント:該当ページ内の特定領域や専用画面への遷移
- メッセージ例:「この機能は管理者のみが利用できます」
これらは設計時にどのエラーがどこで出るかを明示し、UIとともに計画的に組み込む必要があります。
エラー設計で考慮すべき要素
ユーザーにとって「やさしいエラーメッセージ」を実現するには、次のような要素を考慮することが重要です。
原因が伝わる具体的なメッセージ
- 「エラーが発生しました」では不十分
- 何が、なぜ、どうすれば解消できるのかを短く明示
例:「パスワードが8文字未満です。もう一度入力してください」
表示場所とデザインの一貫性
- 全体エラーは画面上部、入力エラーは項目の下など、表示ルールを統一
- 赤系のカラー・アイコン・枠線など、視認性と意味を両立したUI
再操作や回避手段を示す
- 通信エラーであれば「再試行」ボタンを出す
- セッション切れなら「再ログインはこちら」などの誘導
ログ・内部向け情報との分離
- システムログには詳細な例外情報を記録しつつ、ユーザーには分かりやすい文面で出力する
- 技術用語の露出を避ける
提案・見積もり時に確認したいポイント
エラー設計は「UIが完成してから考えるもの」と捉えられがちですが、発注段階でも以下のような観点で提案の質を確認できます。
想定されるエラー一覧が用意されているか
- 画面ごとに、どのようなエラーが発生し得るか洗い出されているか
- バリデーション、通信、業務ロジックの3分類で整理されているか
UI上での表示方法が決まっているか
- 入力欄下に表示?ポップアップ?画面遷移?
- スマホとPCで表示方式が変わらないか
文言やトーンが設計されているか
- 一貫した文体(「〜してください」「〜できません」など)
- 専門用語を避けた説明になっているか
- 翻訳や多言語対応の考慮があるか
再試行やサポートへの導線があるか
- エラー後に再操作できるように戻る/リトライの設計があるか
- エラーの種類によってサポートへの問い合わせ導線が変えられるか
このような情報が提案段階で確認できれば、「エラーは後回し」という開発体制ではないことが分かります。
まとめ:「わかりやすい失敗」がシステム全体の印象を変える
エラーは「うまくいかなかった」という否定的な場面ですが、そこでの対応次第で「ちゃんとしたアプリだな」「丁寧に作られている」といったポジティブな印象を与えることができます。
一方で、エラーメッセージが雑だったり、操作の手詰まりを生むような設計になっていると、どんなに機能が充実していても、ユーザーは使い続けたいとは思わなくなります。
開発を依頼する立場としても、「エラー設計は後からでもよい」とは考えず、ユーザー体験の一部として最初から組み込むことを意識しましょう。
その視点を持つだけでも、システム全体の使いやすさと完成度が大きく変わるはずです。