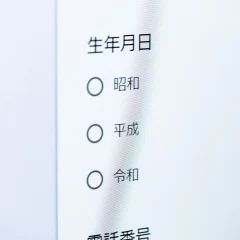アイコン設計の失敗に学ぶ、“わかりやすいUI”のための視覚言語と曖昧さ排除の技術

導入
「分かりやすいUIを作りたい」「直感的な操作を目指す」といった言葉は、システム開発やアプリ開発において頻繁に語られます。その中で、ボタンやナビゲーションに用いられる“アイコン”は、ユーザーにとっての重要なインターフェース要素です。
しかし実際には、見た目が整っていても「何の機能か分からない」「意味が曖昧」「押しても想定通りの動作にならない」といったケースが後を絶ちません。デザインや機能設計において“アイコンの意味性”が軽視されていることが、ユーザー離脱や操作ミスの一因となっているのです。
この記事では、UIデザインの現場でよくある「アイコン設計の失敗例」をもとに、発注者やプロジェクト関係者が確認すべき設計のポイント、そして“曖昧さ”を排除して分かりやすい操作を実現するための視覚的表現の考え方を、実践的に解説します。
アイコン設計に潜む“曖昧さ”の実例
まずは、実際に現場で発生したアイコン設計における典型的な失敗例を紹介します。
1. 意味が伝わらないアイコン
あるシステムで、「グラフ分析機能」にアクセスするために使われていたのは“虫眼鏡+棒グラフ”のアイコンでした。しかし、ユーザーの多くがこれを「検索機能」だと誤解し、誤クリックが続出しました。
→原因:虫眼鏡=検索という認識が先行しており、複合的な意味が伝わらなかった。
2. 意図しない行動を誘発するアイコン
SNS風の通知ベルアイコンが押されると“通知設定”が開く仕様になっていたが、ユーザーは「通知一覧が見られる」と思い込んで混乱。
→原因:「ベル=通知を見る」が一般的な文脈として根付いていたため、異なる機能割り当てがユーザーの期待とズレていた。
3. デザイン優先で意味が希薄に
デザインチームが“ミニマルで統一感のある見た目”を重視した結果、アイコンのシルエットが全て似通ってしまい、ユーザーがどのアイコンが何かを見分けにくくなった。
→原因:ビジュアルとしての美しさが機能の視認性を上回ってしまった。
これらの失敗例に共通するのは、「制作者は理解していても、ユーザーには意味が伝わっていない」という“知識のギャップ”にあります。
なぜ“意味が伝わらないアイコン”が生まれるのか?
アイコン設計が失敗する主な理由は次の通りです。
開発者やデザイナーの「認知バイアス」
作り手は仕様を熟知しているため、「このアイコンが何を意味するか」を分かったつもりでデザインしてしまいがちです。初めて使うユーザーの目線で見直す視点が欠けることで、意味が通じないUIが生まれてしまいます。
社内文化に閉じた「内部用語の視覚化」
とある企業では、“旗マーク”のアイコンが「優先対応フラグ」機能として使われていましたが、社外のユーザーにはまったく意味が伝わりませんでした。社内文化や業務用語に依存した視覚表現は、ユーザー体験を著しく損ないます。
多義的なアイコンの乱用
「星」「三本線」「+」「・・・」などは、アプリごとに異なる意味を持つ場合が多く、コンテキスト(文脈)がないと混乱を招きやすいアイコン群です。こうしたアイコンを安易に使うと、ユーザーが操作をためらう原因になります。
意味の伝達を重視した“わかりやすいUI”設計のポイント
それでは、どのようにして“意味が伝わるアイコン”を設計すればよいのでしょうか?以下の観点が非常に重要です。
1. アイコン+ラベルの併用
最も効果的なのは、初期状態ではアイコン単体ではなく「アイコン+テキスト(ラベル)」を表示すること。これにより認知コストが大幅に下がり、初回利用者でも誤解なく操作できます。
→例:アイコン(💬)だけでなく「メッセージ」と表示する。
2. 一貫性のあるパターン設計
システム全体で、「ベルは通知」「紙飛行機は送信」など、意味とアイコンをセットで設計し、統一感を持たせることで、ユーザーの学習コストを下げられます。
また、異なる画面で同じアイコンが異なる意味を持つのは避けるべきです。
3. ツールチップ・ホバー時の補助表示
PC環境であれば、ホバー時に「このアイコンは何をするのか」を表示するツールチップの実装が非常に効果的です。スマホでもロングプレスなどの補助動作を活用することで、機能の“気づき”を提供できます。
発注者がUI/UXレビューで見るべきポイント
受託開発プロジェクトでは、UIデザインを外部に委託するケースが多いため、発注者が以下の視点で設計レビューを行うことが重要です。
・各アイコンが「何の機能を示すか」明確か?
・ラベルなしで分かるか? 分からない場合の補助があるか?
・ユーザーが誤解しそうな表現はないか?
・似たアイコンが機能的に重複していないか?
・業界標準の意味と乖離していないか?
ユーザーテストやプロトタイプレビューの際に、実際に操作してもらい、「このアイコン、何の意味だと思いましたか?」といった確認をするのも有効です。
コストと効果のバランスを取るには
「ラベルや説明を増やすと、UIがゴチャつくのでは?」という懸念はもっともです。しかし、実際には“使いやすさ”が上回れば、多少の情報量はユーザーの負担になりません。
最も避けたいのは、“見た目がすっきりしていても、意味が伝わらず操作されないUI”を作ってしまうことです。初期段階では“過剰に伝える”くらいで設計し、ユーザーの慣れに応じて徐々に簡素化するアプローチが有効です。
まとめ:「伝わるアイコン設計」は地味だがUI成功の鍵
アイコンは小さなUIパーツですが、その意味伝達に失敗すれば、ユーザーの迷いやストレス、誤操作につながる重大なUX課題になります。
開発を依頼する際には、「どんな機能を、どう伝えるか」というコミュニケーション設計の視点を持ち、アイコンも単なる飾りではなく“視覚言語の一部”として捉えることが、ユーザーに優しいシステム構築の第一歩です。