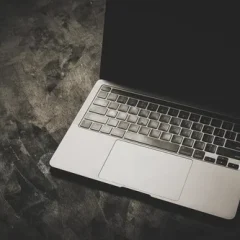システム開発における「設計と実装のねじれ」問題とは?プロジェクトを揺るがす認識ズレの正体

はじめに:仕様書通りなのに期待と違う?開発現場の違和感
システム開発において、よく聞かれる声の一つが「仕様書通りに作ったはずなのに、クライアントの期待とずれている」というものです。 設計に従って実装された機能であっても、実際の運用シーンでは「こうじゃない」「使いにくい」といった声があがり、手戻りや機能修正が発生することも少なくありません。
本記事では、そうした「設計と実装のねじれ」がなぜ起きるのかを掘り下げ、どうすれば事前に防げるのかを開発ノートの視点で解説していきます。
よくある課題:設計レビューで見逃されがちな「認識のズレ」
「要件定義もちゃんとやった」「設計書もレビュー済み」「プロトタイプも見せた」――それでも起こるズレ。
この背景には、以下のような見えにくい課題があります。
- 設計者が「想定していた使い方」と、ユーザーの「実際の使い方」が異なる
- プロトタイプで伝わるのは画面遷移やレイアウトだけで、業務オペレーションの流れは伝わらない
- UIレビューが行われても、UX(使い心地)や入力頻度、手間などは検証されにくい
つまり、設計と実装のねじれは「設計自体の品質」だけでなく、「設計の前提条件の認識共有不足」からも生まれているのです。
設計と実装のねじれが起きるパターン分類
設計と実装の間にズレが生じるケースは、大きく以下の3パターンに分類できます。
- 業務フローの理解不足型
要件定義フェーズでヒアリングが不十分なまま進み、そもそも対象業務の解像度が低いまま設計されているケース。 - UI/UXの解釈相違型
デザインや画面設計は合意できていても、入力頻度や表示条件などの細かい運用ニュアンスがずれているケース。 - 開発者の実装判断による仕様逸脱型
設計上の曖昧な箇所を、開発者の判断で埋めた結果、ユーザー意図と離れてしまうケース。
これらは、設計書や画面定義書では可視化されにくく、リリース後に発覚することが多いのが厄介です。
なぜこの問題が見逃されやすいのか?
この「ねじれ」問題がプロジェクト内で見逃されやすいのは、以下のような構造が背景にあります。
- 各工程が「自分の責任範囲で正しい」と思い込んでしまう
- プロトタイプや画面レビューの際に「本来の業務シーン」までは想定しない
- クライアントも「何が違うのかうまく言語化できない」ことが多い
- QA工程では仕様ベースのテストが中心となり、「使い勝手」まではテストされない
つまり、「技術的に正しい」「ドキュメント通り」という安心感が、逆に問題を見落とさせてしまう要因になっているのです。
どこで防げるのか?3つの注目ポイント
このような「ねじれ」を回避するには、以下の3つのポイントを意識した開発体制の構築が重要です。
1. 業務オペレーションの再現性を上げる要件定義
単なるヒアリングだけでなく、ユーザーの業務を「実際の操作レベルで再現する」ことが重要です。
- フロー図や業務手順書だけでなく、操作動画や業務観察を取り入れる
- ユースケースごとに「例外パターン」や「イレギュラー対応」も洗い出す
- 実際の帳票や業務用語の定義も共有し、言語の揺らぎを排除する
これにより、設計の前提がブレにくくなります。
2. UXシナリオに基づくプロトタイプレビュー
画面ごとのレビューではなく、「1業務単位の流れとしての使いやすさ」を確認することが肝心です。
- 例えば「商品の在庫確認〜発注〜納品登録」までを一連のUXシナリオとして検証する
- 1つの画面のレビューで終わらず、「画面遷移+入力操作+業務時間」のセットで判断する
- モバイル利用や複数端末利用など、利用シーンの再現性を高める
これにより、設計が「点」ではなく「線」で評価されるようになります。
3. 実装段階でのギャップフィードバック体制
設計書に明示されていない仕様判断が必要になったとき、開発者が一人で抱え込まず、相談・確認できる体制が重要です。
- 設計時点で「仕様が曖昧な箇所」をマーキングし、実装時に見直す文化をつくる
- プルリクエストやコードレビューに「ユーザー観点のチェック」を含める
- 実装途中の画面や機能を、社内レビュー+クライアント共有するサイクルを確保
開発スピードよりも「ねじれ修正の早期発見」を重視することで、全体の品質が向上します。
プロジェクト管理に求められる「言語化のリテラシー」
この問題は「開発手法」や「技術選定」だけでなく、「言葉の運用」にも大きく依存しています。 特に設計や要件を言語化する力が問われます。
- 曖昧な表現(「柔軟に対応」「簡単に操作」など)は必ず具体化する
- 専門用語・略語・社内ルールなどは定義を明記する
- 業務用語の定義が食い違っていないかを初期段階で擦り合わせる
「伝わっているはず」「普通そうするはず」などの思い込みは、言語化によって解消できます。
まとめ:設計の“前提”を揃えることが成功の鍵
設計と実装のねじれ問題は、特定の開発工程やスキルの問題というよりも、「認識の同期が不十分」なことが原因で起こります。
要件定義の精度を上げるには、「業務の再現性」「シナリオベースの検証」「曖昧さの早期発見」といった文化の構築が不可欠です。
開発パートナーを選ぶ際は、「こうした設計前提の認識共有にどれだけ丁寧に取り組んでいるか」も、1つの判断基準にしてみてください。