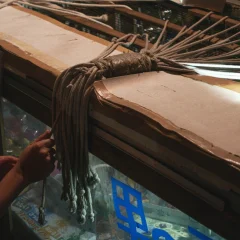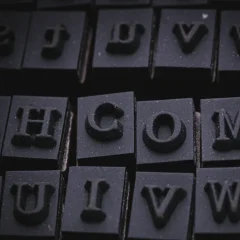SaaSアカウント棚卸し管理システムの構築ノート:シャドーIT対策としての内製導入プロジェクト

SaaSの利用が日常化した現在、企業のIT部門にとって「全社的なアカウント棚卸し」は避けて通れない業務課題です。シャドーITの蔓延、コストの不透明化、情報漏洩リスクなど、見過ごせない影響が多方面に現れます。本記事では、開発受託を検討する企業担当者向けに、「SaaSアカウントの棚卸しと可視化」に特化した業務システム構築の実例をもとに、内製または受託での開発検討時に参考となる技術と実務ポイントを詳述します。
なぜ今「SaaSアカウント棚卸し管理」が必要か
SaaSツールは従業員主導で導入されるケースも多く、組織として正式に把握できていないまま利用が続くことが増えています。これがいわゆる「シャドーIT」です。この状態が続くことで、次のような深刻な課題が発生します。
- 退職者アカウントが放置され、情報漏洩リスクが高まる
- 同じツールを部署ごとに重複契約しており、コストが非効率化
- 経理と情報システム部門で契約管理が非連携、更新漏れが発生
このような状態では、ツールが便利であるがゆえに「使いっぱなし」になる傾向があり、IT資産の全体像すら掴めないという状況が続いてしまいます。そこで、棚卸し業務を定常業務としてシステム化し、「継続的な可視化とコントロール」を実現する必要があります。
システム化の目的と要件定義
今回のプロジェクトでは、アカウント管理における属人性と手動作業からの脱却を目的に、「情報の一元化」と「業務運用への自然な組み込み」を重視しました。以下の要件が具体的に定義されました。
- Google Workspace、Azure AD、Slack、Notionなどからアカウント情報を自動収集
- 各サービスとのAPI連携により月次でクロール・集計処理を実施
- 部門・利用者・契約者・利用中サービス・更新期限をマッピング
- 重複アカウントや利用停止漏れ、契約期限超過の異常を検出し、Slack/Chatで通知
- 管理者ダッシュボードでの横断検索機能とCSVエクスポート対応
業務と技術の両面から、現場に負荷をかけずに運用できるよう工夫されました。
技術スタックと構成概要
システム全体は、拡張性と保守性を意識した構成が取られました。
- フロントエンド:Nuxt.js + Tailwind CSS
- バックエンド:FastAPI(Python) + Celery(非同期ジョブ)
- データベース:Supabase(PostgreSQL)
- 認証基盤:Auth0(RBAC設計込み)
- インフラ:Render + Amazon S3(ログ保存)
- 通知連携:Slack API、Google Chat Webhook
この構成により、運用コストを抑えつつ、月次ジョブの安定運用とリアルタイムな管理ダッシュボードを実現しました。
UI/UXで工夫したポイント
現場のIT担当者が継続的に使い続けられることを重視し、UIでは以下の点にこだわりました。
- ツール別のタブ切り替えでサービスごとのアカウント状況を一望
- 90日以上未使用のアカウントは色付きで視認性を向上
- 契約更新期限が近づくとバナー通知を管理者トップに表示
- 各アカウントに対してメモや会話履歴をコメントで記録可能
操作導線は「今、誰が、何をすべきか」を明示することを重視し、UI/UX設計が業務フローと密に連携するよう意図されました。
開発運用で得られた定量的効果
システム導入から4か月後、以下のような改善が定量的に確認されています。
- 利用中SaaS数:46 → 27件へ削減(重複・放置ツールの排除)
- SaaS費用:月額約23%削減(コスト構造の見直し)
- シャドーITツール検出件数:13件 → 2件に減少
- 棚卸し工数:8時間/月 → 1.5時間/月に短縮
単なるツールの導入にとどまらず、システムとして定着し、「継続的な業務改善サイクル」を生み出す設計が奏功しました。
受託開発パートナー選定の観点
このプロジェクトでは、パートナー選定も成功の重要なファクターでした。以下のような点が高く評価されました。
- 情報セキュリティ要件(ID/パスワード管理、認可設計)への深い理解
- SaaS APIの仕様理解と、連携先が増えても耐えられる拡張設計力
- 管理画面開発の豊富な経験と、UI/UX提案力
- アジャイル/スクラム開発体制と継続改善の文化があること
開発フェーズだけでなく、その後の運用支援・改善提案のフェーズまでを見越して関わる姿勢が、今回の成功につながりました。
まとめ:棚卸し業務こそ「業務資産」としてのシステム構築を
アカウント管理やSaaS棚卸しは、煩雑で属人的になりやすい領域です。だからこそ、システムとして仕組み化することで、運用の継続性と情報セキュリティを両立できるようになります。
表面的な機能要件にとどまらず、「このシステムを3年後も使い続けるには?」という視点で要件を描ける開発会社との協働が、投資効果を最大化する第一歩となるはずです。