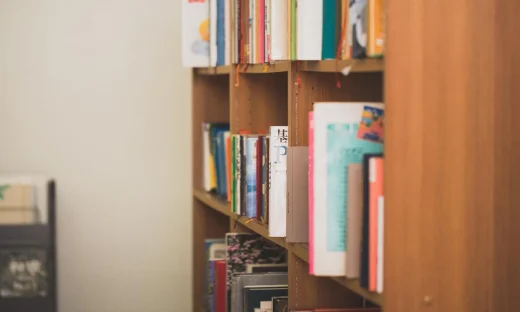サーバー利用状況の可視化とアラート自動化を支える業務システム開発:内部IT部門の負荷軽減を実現したユースケース

企業内IT運用に潜む課題:見えない“異常”への対応遅れ
現代の企業活動において、社内インフラの安定運用は、業務の効率性や信頼性に直結する最重要項目です。ところが、多くの企業では、インフラ監視の体制が後手に回っているケースが散見されます。
たとえば、サーバーのダウンやリソース逼迫といったトラブルが「発生して初めて気づく」といった運用が常態化している企業も少なくありません。特に複数部署が同一インフラを利用している場合、「どの部門が、いつ、どの程度のリソースを消費しているのか」を正確に把握することは困難です。
このような“事後対応型”のIT運用体制では、突発的な障害に翻弄されるばかりか、ユーザー部門からの信頼を損ねる原因にもなります。加えて、対応に追われるIT担当者のストレスや負担は無視できないものがあります。
解決アプローチ:「予兆検知」×「自動通知」による次世代型モニタリングの構築
こうした課題に対して、本ユースケースでは「インフラ利用状況のリアルタイム監視」と「閾値超過時のアラート自動通知」を組み合わせた業務システムを構築することで、根本的な運用改善を目指しました。
このシステムの要件は、単なるインフラの可視化にとどまりません。以下のように、実務の現場で活用しやすく、継続的な運用ができることを前提に設計されました。
-
サーバーやクラウドインスタンスのCPU・メモリ・ディスク使用率を高頻度で収集(10秒間隔)
-
任意の閾値を超えた場合に、Slackやメールに対して即時通知
-
使用状況を部門別にグラフ・数値で可視化し、CSVとして出力可能
-
トレンド把握のため、1年以上のデータ保持機能を実装
-
社内ポリシーに準拠したID・アクセス制御の仕組みを確保
採用された技術スタックと選定理由:柔軟性と拡張性の両立
このシステムの構築にあたり、採用された技術構成は以下の通りです。目的は、社内環境に閉じつつも、クラウドネイティブの拡張性を確保する点にあります。
-
Prometheus Node Exporter:各ノードのメトリクス収集をエージェント型で実現。軽量かつリアルタイム性が高い。
-
Prometheus + Thanos:Thanosにより、Prometheusのメトリクスを1年以上保存しながらスケーラビリティを維持。
-
Alertmanager:ルールベースで閾値を監視し、Slackやメールなどの通知チャネルと連携。
-
Grafana:ダッシュボードによる視覚的なモニタリング。部門別の表示や履歴トラッキングも可能。
-
Next.js + Supabase:CSV出力機能やユーザー画面を開発。Supabaseにより高速なDBレスポンスとFirebaseライクな運用性を両立。
-
Auth0:シングルサインオンや社内アカウント連携に対応。権限レベルによるアクセス制御を実装。
特筆すべきは、クラウドベースながらオンプレミスとの橋渡しが可能で、セキュアな運用体制を維持しながら機能性を高めている点です。
導入後の効果:可視化による“対応から予防”へのシフト
システム導入後、IT部門では明確な成果が見られました。とくに「障害の予兆検知による予防型対応」が大きな変化として現れています。
-
障害発生件数の削減:月間8件発生していたダウンや障害対応が、平均2件にまで減少(約75%の削減)。
-
問い合わせ対応工数の短縮:ユーザーからの確認依頼や原因調査にかかる時間が、平均で30分以上短縮。
-
インフラ拡張コストの最適化:トレンドデータに基づいた増設計画により、不要なリソース購入が抑制された。
さらに、アラート通知によって即時に関係者が情報を共有できるようになり、「事後対応から事前調整へ」という文化の醸成にも寄与しています。
受託開発会社の選定で求められる「業務理解と技術融合力」
このプロジェクトで成功の鍵を握ったのは、「単なる監視システムの導入」ではなく、「業務フローに合致した形でのカスタマイズ提案と実装」です。
発注側である社内IT部門は、以下のような条件で開発会社を選定しました。
-
クラウド基盤・監視系インフラの技術実績がある
-
部門間での共同運用を想定したUI/UX設計力
-
DevOpsやSRE(Site Reliability Engineering)の実務経験
-
社内ネットワーク環境や情報セキュリティ規約に対する理解と配慮
こうした条件に応えられる受託開発会社こそ、単なる外注先ではなく、社内IT変革を支えるパートナーとしての役割を果たすことができます。
今後の展望:自動化による“IT部門の変革”を支える文化づくり
今回の導入は、あくまで「サーバー監視の自動化」が主眼でしたが、ここを起点として、将来的には以下のような展開が見込まれています。
-
ネットワーク帯域やアプリケーションレイヤーの監視範囲の拡張
-
チケット管理ツールとの連携(例:Jira、Backlog)によるインシデント管理
-
AIベースの異常検知(Anomaly Detection)によるさらなる予兆対応の高度化
-
RPAやIaC(Infrastructure as Code)との連携によるフルオートメーション運用
このように、小さな自動化の積み重ねが、やがて組織の運用そのものを変えていく基盤となるのです。
まとめ:「見える化と自動化」が組織の成熟を加速させる
社内インフラの運用改善は、一見すると地味なテーマに見えるかもしれません。しかし、それは企業全体のDX基盤となる重要な土台であり、「見える化」と「自動化」を通じて、IT部門のあり方を抜本的に変える可能性を秘めています。
今回の事例が示すように、技術と業務知識の橋渡しを担える開発会社の支援があってこそ、こうした運用変革は実現可能です。小さく始めて大きな成果を導く、その第一歩として、本記事が一助となれば幸いです。