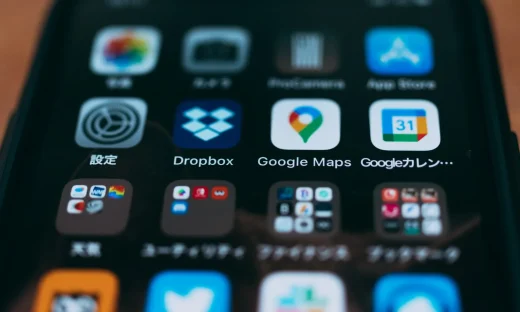リサイクル業界のDXを支える|買取・査定・在庫を一元管理する業務システムの開発ユースケース

導入:リユース業界の業務は「分断されすぎている」
ブランド品や古着、家電、ゲームソフト、骨董品など、多種多様な商品を扱うリユース(中古買取)業界は、今まさに変革の時を迎えています。
店舗に加えてネット販売(EC)も当たり前、複数店舗の在庫連携、リアルタイムの査定管理など、業務の複雑さは増す一方。しかし現場では、「Excelでの管理」「メールや電話での査定依頼」「システムが分かれていて二重入力」など、アナログな運用がいまだに主流です。
今回は、そんな課題を抱えていた地方のリサイクルチェーン企業が、業務全体を一元化する**「買取・査定・在庫管理システム」**を新たに開発した事例をご紹介します。業界にありがちな“よくある困りごと”と、それをどう解決したかを、システム開発視点から深掘りしていきます。
ユースケース概要:買取から販売までの業務を一気通貫で管理
今回の開発プロジェクトでは、以下のような業務フローを一元的に管理するシステムを構築しました。
-
来店またはLINE・WEBからの買取査定依頼受付
-
担当者による査定額の提示と承認管理
-
査定結果を元に商品の買取登録
-
商品情報(カテゴリ、ブランド、状態など)と写真を一括登録
-
倉庫在庫と店舗在庫の分離管理
-
ECモール(楽天・Yahoo・自社サイト)への商品情報自動連携
-
商品売却後、在庫反映とレポート出力
-
各店舗での買取件数・売上・在庫回転率のダッシュボード管理
対応範囲は多岐に渡るが、要件整理が成功の鍵
このプロジェクトでは、「フルスクラッチ開発」で業務フローに最適化された設計が行われました。要件の中心は、現場の声を拾い上げながら、
-
アナログ運用のどこがネックか?
-
システム化することでどれだけ業務工数が減るか?
-
どの情報を誰がいつ入力・更新すべきか?
といった“実務に根差した設計”が徹底された点が大きな成功要因となっています。
開発の背景:「システムが増えすぎて、逆に非効率」
もともとこの企業では、以下のような分断されたシステムが運用されていました。
-
買取管理:紙ベース+店舗内ローカルExcel
-
査定業務:メール+チャット+印刷物
-
商品登録:EC専用システムと店舗POSが別々
-
在庫管理:店頭在庫と倉庫在庫が一元管理されていない
-
売上管理:各チャネルでCSV出力→手動集計
これにより起きていた問題は、
-
入力ミス、重複、属人化
-
担当者ごとに処理の仕方が異なる
-
査定の履歴が残らず、トラブル時の証拠がない
-
ECとの在庫差異が頻発(売れたのに店頭に残っている)
-
仕入から売却までのコスト管理ができない
これらの課題を統合的に解決するため、「業務システムとしての一元化」が必要となったのです。
システムの主な構成と技術的ポイント
開発にあたっては、以下のような技術的アーキテクチャが採用されました。
-
バックエンド:Laravel(PHP)+MySQL
-
フロントエンド:Vue.js+TailwindCSS
-
インフラ:AWS(ECS/RDS/S3/CloudFront)
-
外部連携:楽天・Yahooの商品API、LINE連携、Google認証
-
管理画面:SPA構成でスタッフ操作のUIを高速化
-
画像管理:S3とCloudFrontによるCDNキャッシュ
特に、査定~商品登録のUIは「スマホでも完結できる」ように設計され、倉庫スタッフが現場で撮影→商品登録→価格設定まで行える構成になっています。
結果として得られた業務改善効果
導入後、以下のような定量的成果が出ています。
-
商品登録作業が平均15分→5分に短縮
-
査定対応の平均リードタイムが48時間→12時間へ
-
ECと店舗在庫の差異が95%以上解消
-
スタッフ間の業務属人性がほぼゼロに
-
店舗間の商品移動管理が自動記録され、棚卸の作業時間を60%削減
また、ダッシュボードで日次の売上・在庫回転率・買取件数などが可視化されたことで、「数値に基づいた判断と仕入戦略」が実現されています。
開発会社選定時に重視した観点
発注企業が特に評価したポイントは以下です。
-
「業界理解」を踏まえたヒアリング力
-
要件を粒度高くブレイクダウンする提案力
-
査定・買取・販売の分離設計(ドメイン分割)の知見
-
EC API連携など“実装しにくい領域”への対応力
-
運用フェーズを見据えた「設定項目」や「ログ管理」設計の丁寧さ
このような実務への深い理解をベースにした開発パートナーとの協働が、プロジェクト成功の鍵を握っていました。
発注側が意識すべき設計視点とは?
同様のシステムを検討する際には、以下のような視点が重要です。
-
「査定」「在庫」「販売」「買取」は別のドメインと捉えて整理する
-
店舗とECの両方に適用するUIをどう設計するか?
-
商品ステータス(査定中/出品中/売却済/返却など)の状態遷移は整理済か?
-
業務ごとの担当者権限と操作範囲は分離できているか?
-
「CSVでの一括操作」は必要か?逆に危険か?
-
EC連携APIはリアルタイムかバッチか?どのくらいの頻度か?
これらの観点を要件定義段階で押さえることで、開発後のトラブルや想定外の費用増を防ぐことができます。
まとめ:リユース業界にも“システム設計の筋肉”が必要だ
本記事で紹介したように、リユース業界においてもシステムの重要性は年々高まっています。特に「アナログな業務×在庫×EC」という複雑な領域では、部分的なツール導入では限界があり、業務全体を一貫して支える業務システムの構築が求められます。
開発会社を選ぶ際は、単に技術力だけでなく、業務構造そのものを理解・設計できる“提案型”のパートナーを選ぶことが、DX推進の成否を大きく左右するでしょう。