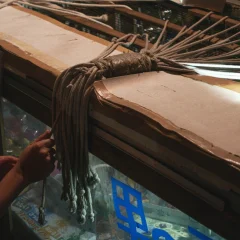店舗スタッフの声から生まれた「在庫不足アラート連携システム」構築事例:販売現場主導のDXが売上を変える

小売業や飲食業の多店舗展開企業では、日々の店舗運営を支える現場スタッフの業務効率が、売上や顧客満足度に直結します。特に、在庫補充のタイミング判断を属人的に頼っている店舗では、「売れ筋商品の欠品」が売上機会の損失に直結する課題となっています。
この記事では、店舗スタッフの「気づき」をもとに構築された「在庫不足アラート連携システム」の開発ユースケースを通じて、業務システム開発における「現場主導のアプローチ」や受託開発パートナーとしての支援視点を詳しく解説します。
背景:POSデータはあるのに在庫補充が遅れる理由
対象となったのは、全国に40店舗を展開する生活雑貨チェーン企業です。同社ではPOSシステムを導入済みであり、販売データや在庫数の集計は本部で行われていました。
しかし、実際の店舗では以下のような「補充の遅れ」が頻発していました。
- 本部集計から店舗へのフィードバックに2〜3日かかっていた
- 売上数と在庫数の差だけでは補充判断が難しく、店頭の感覚に依存
- 店舗スタッフは在庫不足に気づいても、本部への報告手段が非効率(電話・メール)
- 補充依頼の優先順位が不明確なまま、本部が対応に追われていた
このような状況は、「本部と現場間の情報の非対称性」が主因であり、システム的な連携不足による業務の停滞を招いていました。
要件定義:現場発想と本部運用の両立を実現するために
本プロジェクトでは、現場のフローを重視した以下の要件が定義されました。
- 店舗スタッフが「売れ筋商品の在庫切れの兆候」に気づいたとき、スマホからすぐにアラートを送信できる
- アラートは本部の専用ダッシュボードに集約表示
- 優先度(売上構成比、季節性、前回補充からの経過日数など)に応じて補充依頼の自動並び替え
- 本部はダッシュボードから発注ステータスを更新し、店舗へ通知
- アラート送信後24時間以内の本部対応率をKPIとしてモニタリング
特に意識されたのは、「本部主導」ではなく「現場主導の気づきを活かす仕組み」をシステムに組み込むことでした。さらに、現場に負担がかからないよう「操作簡素化」「視認性の高さ」「通知の確実性」が追求されました。
技術構成と開発体制:スモールスタートでの高速展開
本プロジェクトは、まず3店舗での実証導入から始まりました。開発期間は約1.5ヶ月、以下のような構成でスピーディに構築されました。
- フロントエンド(店舗用):React Native(スマホネイティブアプリ化)
- フロントエンド(本部用):Next.js(社内Webダッシュボード)
- バックエンド:Firebase Functions + Firestore
- 通知連携:Slack API(本部担当者へ即時通知)
- 権限設計:Firebase Auth + RBAC
- データ集計:BigQuery + Looker Studio
この構成は、ローコスト・高柔軟性を実現しつつ、初期導入後の展開拡張にも備えたスケーラブルなアーキテクチャとして評価されました。
UI/UXへの配慮:忙しい店舗でも「1タップで報告」できる導線設計
店舗スタッフは、常にお客様対応やレジ業務などで忙しく、「複雑なアプリ操作に時間を割けない」という事情があります。そこでUI設計では以下の工夫が施されました。
- 店頭のスマホから1画面内で完結する「在庫アラート」入力画面(商品名選択・理由タグ・コメント入力)
- よく使うアラートテンプレートの登録機能により、入力時間を30秒以内に短縮
- アラート送信後の「対応ステータス」が色分けで確認できるタイムライン表示
- 操作ログは自動で記録され、再操作不要
- オフライン環境下でもアラート下書き保存が可能
また、システム利用時の初期オンボーディングは「現場チーフ向け10分マニュアル」に集約し、短期間での定着を実現しました。さらに、動画チュートリアルやFAQも併設することで、導入初期の混乱を最小限に抑えました。
効果測定:定量・定性での成果
導入から3ヶ月間で、以下のような成果が実際に記録されました。
- 売上トップ20商品の欠品率:15.7% → 5.2%へ改善
- 本部による在庫補充対応の平均リードタイム:2.4日 → 0.9日へ短縮
- アラート送信数のうち、24時間以内の対応完了:82%
- 現場スタッフの業務満足度(社内アンケート):94%が「有用」と回答
さらに、現場スタッフの「自主的な気づき」が数値化されたことで、現場のモチベーション向上にもつながりました。現場→本部→再フィードバックという可視化されたサイクルは、継続的な業務改善文化を形成し始めています。
受託開発会社として評価されたポイント
本案件で受託開発パートナーが評価されたのは、以下の観点でした。
- 「現場ヒアリングを通じた業務理解」と「UXに反映された設計力」
- FirebaseやSlackなど、スピードとコスト最適の技術選定
- 小規模フェーズでPoC導入→段階的なスケーリング提案
- プロトタイプを起点とした非エンジニアとのスムーズな合意形成
- 店舗と本部、両者の業務要件を踏まえた「現実解としての開発提案」
単なる受託開発ではなく、「現場の業務と密接に結びついた設計提案」が評価の決め手となりました。
まとめ:「現場の気づき」が起点になる業務システム開発の価値
在庫アラートのような一見「小さな仕組み」も、現場業務とテクノロジーをつなぐ起点となれば、業務改善と売上向上の大きな成果に直結します。
受託開発会社としては、単なる機能提供にとどまらず、「誰の、どんな行動を変えるための開発か?」という視点を持ち、ユーザーと共創するスタンスがより一層重要になってきています。
今後は、在庫補充にとどまらず、売場演出の改善提案、来店客数の変動予測、店舗間連携など、「現場起点の発想」をシステム化する動きが加速していくことでしょう。