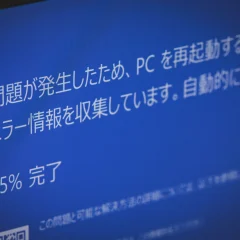自治体向け予約管理・抽選システムの開発事例|多様な住民サービスに対応する業務効率化と利用者体験向上の両立

導入:自治体サービスの「予約と抽選」は、なぜこんなに煩雑なのか?
公共施設の利用や住民サービスを巡る“予約・抽選”業務は、自治体職員にとって大きな負担となっています。
たとえば、
・公民館や体育施設の貸出予約
・予防接種や健康診断の時間枠予約
・講座やイベントの定員制申込(先着順 or 抽選)
・高倍率な申し込み枠の抽選結果通知
こうした業務の多くは、いまだに電話や窓口受付、Excelでの転記管理といったアナログ運用に依存しており、
「同じ電話番号から何度も申し込まれて困る」
「予約時間の重複やダブルブッキングが発生してしまう」
「抽選の公平性をどう担保するか分からない」
といった問題が日常的に起きています。
本記事では、ある地方自治体で実際に導入された「予約・抽選管理システム」の開発事例をもとに、
発注側が意識すべき視点やシステム設計の工夫、費用対効果の考え方を具体的に解説していきます。
ユースケース概要:複数種別の予約・抽選を一元管理
対象の自治体では、住民サービスごとにバラバラだった受付・管理業務を「1つのシステム」で統合しました。
具体的には以下のような業務が対象です:
-
公民館・体育館・調理室などの施設利用予約(抽選 or 先着順)
-
健康診断・予防接種などの時間枠予約(年齢条件付き)
-
市民向け講座の応募・キャンセル・補欠管理
-
抽選結果の自動通知・当選者確認ページの提供
-
窓口職員による代理申込・予約変更対応
このように、利用対象・予約方式・入力項目が異なる多様な業務に対して、“設定型の管理画面”を設けることで運用の柔軟性を確保しつつ、住民側のUXも統一する設計が求められました。
システム開発の要件と工夫ポイント
今回のシステム開発では、以下のような要件が提示されました。
住民側の要件
-
スマホで完結する申込・キャンセルフロー
-
抽選結果やリマインド通知をLINE・メールで受信
-
家族分の申し込み/代理申し込みにも対応
-
アカウント登録なしでも申込可能(認証は予約番号と生年月日)
管理側の要件
-
業務ごとに受付期間・定員・応募条件を設定できる
-
予約や抽選の受付・キャンセル・当選連絡を一元管理
-
ログ・履歴の記録、CSV出力、電話申込の代理入力機能
-
高齢者向け操作支援(紙ベースの予約受付→後入力も可)
特に評価されたのは、**抽選ロジックをシステム化することで「公平性の担保」「問い合わせ削減」**が実現された点でした。
技術スタックとセキュリティ配慮
システムは以下のような構成で開発されました。
-
フロントエンド:Vue.js(スマホ対応・アクセシビリティ対応)
-
バックエンド:Laravel(PHP)
-
DB:MySQL(予約・応募データを正規化設計)
-
通知:SendGrid(メール)/LINE Notify
-
インフラ:AWS(RDS・S3・WAF)
-
セキュリティ:SSL/WAF/ログインIP制限/認証コードによる本人確認
また、以下の点が行政案件ならではの要件として求められました:
-
データは国内リージョンでのみ保存
-
操作ログは6年間保存(住民訴訟等を見据えて)
-
同一IPからの不正申込を制限
-
アクセシビリティ配慮(音声読み上げ対応)
開発プロセス:住民と職員双方の声を反映したアジャイル設計
行政案件はウォーターフォール型になりがちですが、今回は以下の理由で段階的なアジャイル開発が採用されました。
-
多様な部局が使うため、要件が途中で具体化される
-
住民からの声をデモ版で確認し、UXを調整する必要があった
-
本稼働前にテスト予約期間を設け、負荷や運用負荷を事前検証した
その結果、「職員も納得し、住民も使える」形に仕上げることができました。
成果と費用対効果:どのような効果が得られたか?
実際に導入された年のデータでは、以下のような効果が見られました。
-
窓口・電話予約対応の業務時間が月100時間以上削減
-
抽選業務に関する問い合わせ件数が80%減少
-
市民アンケートで「予約のしやすさ」が前年比30%向上
-
職員の属人業務が解消、誰でも代理対応が可能に
また、再利用性のある設計としたことで、翌年には新たな講座予約にも転用され、追加開発コストも抑制されました。
今後の展開と“中長期で見た価値”
このような自治体向けシステムは、「一度作ったら終わり」ではなく、住民ニーズや制度変更に応じて継続的な見直しが必要です。
そのため、以下のような設計思想が盛り込まれました:
-
管理画面から「予約種別」「応募条件」「定員方式」を自由に変更できる
-
抽選方式も「先着順/完全抽選/部分抽選」などを選択可能
-
職員ごとの操作ログ管理、変更履歴のトレース機能
-
今後の拡張として「APIによる住民ID連携」や「窓口タブレット受付」も想定
このように、“仕様書で固定されない柔軟性”を持った構造こそが、費用対効果の高い公共システムであると評価されています。
発注担当者が押さえるべき開発視点
-
機能ではなく「運用フロー」を主軸に設計を考える
-
アナログ運用の「不満点」「転記のムダ」をすべて棚卸しする
-
利用者(住民)視点だけでなく「職員が運用しやすいか」を優先
-
抽選結果や応募履歴など「問い合わせに耐えうる設計」になっているか
-
操作ログ、監査ログ、出力仕様なども初期から仕様に入れる
自治体案件は“トラブルにならないこと”が重視されるため、実装よりも「安心できる仕組み」が何よりも価値になります。
まとめ:小さな自治体でもDXはできる。鍵は“柔軟性と安心設計”
今回の予約・抽選管理システムの開発事例は、大都市圏ではない地方自治体での実装でした。
予算も潤沢とは言えない中で、それでも「住民サービスをよりよくしたい」という現場の思いが形になった成功例です。
発注を検討している自治体や関連団体の担当者にとっては、「大がかりなパッケージ導入」ではなく、目的に絞った“設計型の受託開発”という選択肢が現実的であることを、ぜひ知っていただきたいと考えています。