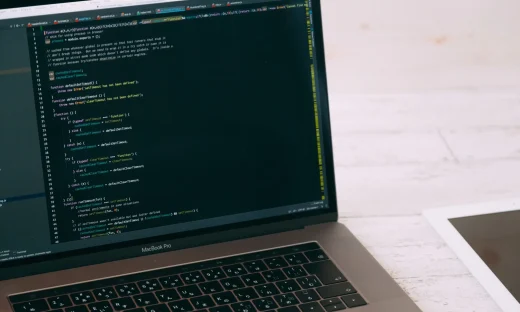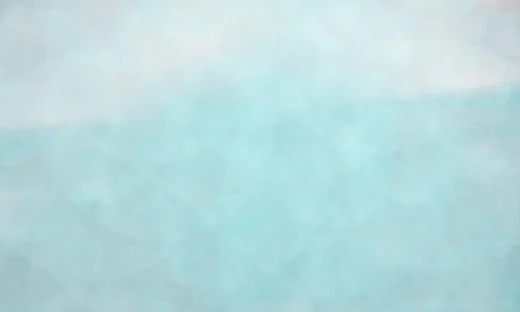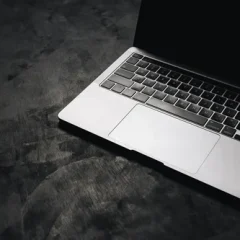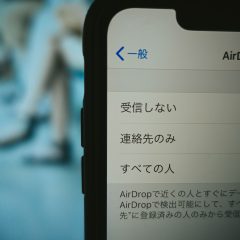複数業者と連携する「分散型開発プロジェクト」の進め方と成功の鍵

開発プロジェクトの発注において、1社にすべてを依頼するという方法は今も主流ですが、近年では目的に応じて複数の業者を使い分ける「分散型開発プロジェクト」の形態が注目を集めています。たとえば、UI/UXはデザインに強い会社に、バックエンドは堅牢な業務システムの開発実績を持つ業者に、というように、それぞれの強みに特化した受託先と協働することで、コストパフォーマンスの最大化と高品質なアウトプットの両立を目指せます。
この記事では、「分散型開発プロジェクト」の具体的なユースケースを通じて、実際の進行方法や注意点、プロジェクト管理の工夫などを掘り下げて解説します。
分散型開発とは何か?メリットと背景
専門性の高いパートナーを選定できる時代
クラウドサービスやAPI連携、コンポーネントベース開発の普及により、アプリやシステムを複数の開発会社で分担して作るハードルが下がっています。これにより、デザインや要件定義に特化した会社、業務システムやモバイルアプリに強い会社など、専門性を最大限活用できる構成が実現しやすくなりました。
リスク分散とコスト最適化
1社依存によるベンダーロックインを避けられることも大きなメリットです。また、特定の領域だけ外注し、自社開発チームと連携するハイブリッドな形態を取ることで、コスト削減や柔軟なスケーリングも可能となります。
具体的なユースケース:「業務基幹+スマホアプリ」分離開発の成功例
プロジェクト背景
ある中小企業では、既存の販売管理システムのリニューアルとともに、スマホアプリによる現場入力機能を新たに導入する必要がありました。この要件は明確に2つの領域に分かれていたため、以下のように開発を分散しました。
-
基幹業務システム(Webベース):既存の業務フローに精通したSIerに依頼
-
現場入力用アプリ(Flutter):UI/UXに強くクロスプラットフォーム対応が得意なモバイルアプリ会社に依頼
分散体制での進め方
-
要件定義は自社が主導し、両社と合同で実施
-
API仕様は業務システム会社が設計し、アプリ側に提供
-
テストはそれぞれで実施した後、受け入れ検証のみ一括で実施
成果と学び
各社が得意な領域に集中できたことで、短期間での高品質なアウトプットを実現。また、システム設計やAPI連携の境界が明確だったため、トラブルも最小限に抑えられました。
分散型プロジェクトを成功させる5つのポイント
1. 共通言語となる仕様書の整備
複数業者が関わる場合、認識のズレが命取りになります。要件定義書、画面設計書、API仕様書などを標準化し、どの業者でも理解できる形でドキュメントを整備することが極めて重要です。
2. プロジェクトマネジメントは自社主導で
分散開発では調整役が必須です。外部PMに任せるケースもありますが、理想は社内に進行管理と判断を担う責任者を置くこと。プロジェクト進行やスケジュール管理において「中立な調整者」が必要になります。
3. API連携を前提に設計する
バックエンドとフロントエンド、あるいは業務システムと外部サービスなど、複数システムの連携はAPI設計に集約されます。責任範囲の分離とスムーズなテスト進行のためにも、最初に「APIファースト」で設計を進めることが効果的です。
4. チャットツールと進行ルールの徹底
複数の開発会社とのやりとりでは、SlackやBacklogなどのチャット・タスク管理ツールが必須です。「質問の仕方」「進行レポートの頻度」「成果物の命名ルール」なども統一しておくことで、やりとりがスムーズになります。
5. 検収プロセスを明確に
検収の条件が不明確だと、納品後のトラブルにつながります。分割納品や段階的検収など、プロジェクト規模に応じた検収ステップを設けましょう。
分散型開発のデメリットとその対策
デメリット1:責任の所在が曖昧になりがち
→ 対策:WBSに責任者を明記、業務分担表を設ける
デメリット2:連携不備による品質低下リスク
→ 対策:モックAPIやテスト用スタブで連携事前検証を行う
デメリット3:コミュニケーション工数が増える
→ 対策:週次定例と日次レポートのルール化
今後注目される「協業型システム開発」のトレンド
分散開発は今後さらに進化し、以下のような形に発展していくと考えられます。
-
複数業者+自社チームによるハイブリッド型開発
-
開発実装はオフショア、要件定義と設計は国内
-
小さなモジュール単位でのマイクロ発注(マイクロ開発)
このようなトレンドの中で、自社がプロジェクトの「舵取り役」としてどう立ち回るかが問われる時代になっていきます。
まとめ
「分散型開発プロジェクト」は、適切なパートナー選定と緻密なプロジェクト設計により、高品質かつ効率的なシステム構築を実現できる手法です。特に、受託開発先を探している企業担当者にとっては、1社完結の固定観念にとらわれず、領域ごとに最適な会社を選ぶ視点がますます重要になってきています。
発注前の情報収集や見積もり比較の中で、こうした「複数社連携」の可能性もぜひ選択肢に加えていただければと思います。