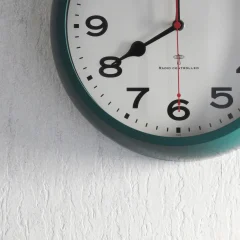訪問介護現場の業務効率化を支える“訪問記録アプリ”の開発ユースケース|高齢者福祉の現場とITの接点とは?

訪問介護の現場で求められる「記録のDX」
訪問介護(ホームヘルプ)サービスは、利用者の自宅に介護職員が訪問して、身体介助や生活支援を行う福祉サービスです。その中で最も煩雑かつ属人的になりやすい業務が、「サービス提供記録の作成」です。
訪問記録には、以下のような情報が含まれます。
-
利用者の体調や様子
-
実施した支援内容(排泄介助、掃除、調理など)
-
予定と実績の差分(滞在時間など)
-
次回訪問に向けた注意点や報告
多くの現場では、これらを訪問後に紙の報告書として記入・回収し、事務所に戻ってから再入力するという非効率な運用が続いています。
こうした背景から、スマートフォンやタブレットで記録できる訪問記録アプリのニーズが急増しているのです。
導入企業と目的:地域介護事業者による現場業務の効率化
本記事で紹介する開発事例は、地方都市に拠点を持つ訪問介護事業所が、以下の課題を解決するために依頼したプロジェクトです。
-
記録業務の紙運用をやめたい
-
サービス実績データをリアルタイムで確認したい
-
管理者が記録をすぐに確認・指導できるようにしたい
-
利用者ごとの注意事項(アレルギーや生活習慣など)を現場で参照したい
-
労働時間削減・スタッフ満足度向上につなげたい
このように、システム化による目的は単なる業務効率化ではなく、人材定着率やサービス品質向上まで視野に入れた設計が求められていました。
主要機能と設計のポイント
開発されたアプリは、介護スタッフ向けにスマートフォン・タブレットで操作できるモバイルアプリとして設計されました。主要な機能は以下のとおりです。
● スケジュール表示
本日担当する訪問先と訪問時間をリスト化。事業所のスケジュール変更もリアルタイムに反映。
● 訪問チェックイン/チェックアウト
位置情報(GPS)と連携して、自宅訪問の開始・終了を記録。介護報酬上の実績証明にも活用。
● 記録入力
チェック形式+フリーコメント入力のハイブリッド方式。サービス内容・気づき・異変・バイタル情報などを記録可能。
● 写真添付・音声メモ
認知症の利用者や生活環境の記録に、画像や音声メモを活用。
● 事業所管理画面(Web)
スタッフが入力した記録を事業所側でリアルタイムに確認・指導。保管・出力・修正も可能。
技術的課題と工夫
介護業務ならではの特殊性から、開発では次のような課題が発生し、それぞれに工夫が施されました。
● 通信が不安定な地域も多い
→ 「一時保存」機能を設け、圏外でも記録できる仕組みに。オンライン接続時に自動同期。
● 利用者ごとに記録項目が異なる
→ サービス提供責任者が個別にテンプレートを設定できるカスタマイズ機能を実装。
● 誤入力・書き直しが多い現場
→ スマホでの誤操作防止のため、大きめのタッチUI、入力ガイド、選択肢による補助機能を強化。
● GPSによる位置取得の精度
→ 記録時に位置確認とあわせて手動チェックもできる二重チェック機構を導入。
● セキュリティ・個人情報対策
→ 端末にデータを保持せず、記録は全てクラウド側に保存。認証はFace IDまたはパスコード併用。
保守運用における要件設計
福祉分野は法令・報酬体系の改正も多く、リリース後の運用設計が極めて重要です。
本プロジェクトでは、以下の運用要件を開発段階から組み込んでいます。
-
システムアップデートは月次で反映しやすい構成に
-
記録テンプレートの柔軟な更新が管理画面から可能
-
データのバックアップとログ保存ポリシーを策定
-
スタッフの操作履歴・記録ミスを可視化
-
複数の事業所間での機能横展開を想定した設計
これらにより、現場の変化や制度の改正に強い「運用できるシステム」を実現しています。
発注者との要件定義で特に重視した視点
介護業務アプリの要件定義においては、以下のような視点が特に重視されました。
-
法定帳票(提供記録/業務日報など)との整合性
-
事業所ごとの運用フローの違いに対応できる柔軟性
-
利用者家族との連携(データ共有/報告)への拡張性
-
管理職による記録確認・フィードバックのしやすさ
-
スマホ操作に慣れていないスタッフへのUX配慮
こうした視点を開発会社が丁寧にヒアリングし、実運用を理解した設計提案ができるかどうかが成功の分かれ目となります。
まとめ:システムは現場に“自然に溶け込む”ことが成功の鍵
訪問介護アプリの開発ユースケースでは、システム導入の目的が単なる「IT化」ではなく、
-
記録ミス・業務負荷の削減
-
サービス品質と安全性の向上
-
職員の満足度向上と離職防止
-
データによる経営判断のサポート
といった多角的な価値を実現するものでした。
特に介護現場においては、「誰が使うか」「どのような負担があるか」を念頭に置いた開発設計が不可欠です。
開発パートナー選定の際には、こうした福祉特有の業務理解や、法令・運用の観点からも設計を提案してくれる開発会社を選ぶことが、成功の鍵となるでしょう。