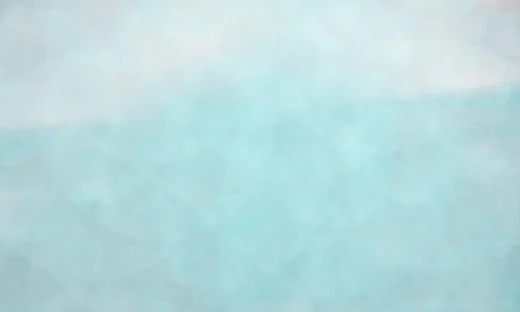フィールド業務の分担混乱を解消した「訪問ルート可視化・調整システム」構築事例:現場対応型DXの新機軸

はじめに:訪問業務の「分担混乱」はなぜ起きるのか?
訪問営業、フィールドメンテナンス、在宅医療、物流、清掃サービスなど「複数スタッフが外部で作業を行う」業種において、現場での業務分担や訪問スケジュールの調整は、事業運営の中核とも言える重要課題です。特に、突発的な案件追加やキャンセルが頻発する運用現場では、紙台帳やExcelによる管理が破綻をきたしやすく、現場責任者やスタッフの負担が急増する傾向にあります。
属人的な調整によって発生する「二重訪問」「移動距離の無駄」「訪問忘れ」などの問題は、企業のサービス品質や顧客満足度に直結します。本記事では、こうした問題を根本から解決した、ある中堅設備保守会社のDX事例をもとに、「訪問ルートの可視化と分担調整のシステム化」をどのように実現したのかを詳しく解説します。
背景:紙台帳と電話での分担調整が限界に達した現場
導入前の状況では、拠点ごとの支社で日々の作業スケジュールを手作業で作成しており、調整業務は電話やメールに頼っていました。これにより以下のような実務上の限界が明らかになっていました。
- 同じエリアに異なるチームが同時訪問する「ルート重複」が発生し、無駄な移動コストが発生
- 作業キャンセルの情報が他のスタッフに即時に伝わらず、空きスロットを活かせない
- 拠点責任者が終日スケジュール調整に追われ、本来のマネジメントに集中できない
- 日報と訪問スケジュールの突合に手間がかかり、報告業務が月末に集中
こうした状況を受けて、現場に即した業務支援システムの構築が求められるようになりました。
要件定義:ルート調整と情報同期の“見える化”を軸に
システムに求められたのは「現場スタッフが自分の訪問計画を可視化・調整できる」「管理者が全体最適を図れる」「変化に即応できる柔軟な仕組み」であること。具体的には、以下のような機能要件が明確に設定されました。
- スタッフごとの訪問予定をGoogleマップ上に可視化し、移動順とルート効率を見える化
- リアルタイムでの訪問依頼/キャンセル通知によるスケジュール自動更新
- 拠点をまたいだスケジュール調整とスタッフ割り振り
- スタッフ間で「この訪問先を代わってほしい」という依頼や「自分が代行可能」の申請
- GPSベースの作業開始・終了ログ取得による自動実績記録と位置情報連携
また、これらの機能を支えるUI/UX設計においては「スマホで誰でも直感的に扱えること」が最優先要件として設定されました。
技術構成と開発体制:迅速なPoCから拡張性ある構築へ
プロジェクトは、5ヶ月間のアジャイル開発で進行。初期段階では5拠点を対象としたPoCを展開し、現場フィードバックを迅速に反映しながら仕様をブラッシュアップしていきました。
- フロントエンド:Flutter(スマホアプリ)/React(Web管理画面)
- バックエンド:Firebase Functions/Firestore によるスケーラブルな構成
- ルート最適化:Google Maps Distance Matrix API による経路計算
- 通知連携:Slack API/LINE Messaging API による状況連携
- ログ解析・レポート:BigQuery/Looker Studio による可視化
開発メンバーは受託会社のエンジニア5名と、クライアント側の業務部門2名による混成チーム。現場での業務理解とフィードバックループを重視した開発体制が構築されました。
UI/UXの工夫:複雑な操作なしで現場が動く仕組みを
システムの利用者は、現場作業に追われるスタッフと、多拠点の状況を把握すべき管理者の両方。それぞれのニーズに合わせた画面・導線設計が重要視されました。
- 地図上に訪問先と経路を重ねて表示、訪問ステータスによる色分け
- スケジュールに空きがあるスタッフをワンタップで提案可能
- 拠点をまたぐ予定変更時もルート重複をアラートで通知
- 訪問状況に応じて「代理依頼ボタン」「譲渡申請」などのボタンを表示切り替え
- 通知には簡易ルート付き、Slack・LINEから地図リンクへ直遷移
「マニュアルなしでも使えるUI」を目指すことで、全社展開時の教育コストを最小限に抑える工夫がなされました。
定量成果と現場の変化
システム導入後、業務指標にも明確な変化が現れました。
- 二重訪問や無駄な移動の発生:月45件 → 月3件に激減
- 未訪問・対応漏れ案件:月17件 → 月1件未満へ
- 当日急対応(代理含む):48% → 81%へ上昇
- 月次レポート作成時間:3.2人日 → 0.8人日に圧縮
さらに、拠点長からは「スケジュール調整の電話対応が激減し、他業務に集中できるようになった」との声も上がっており、業務品質と効率化の両面で高い効果が出ています。
受託開発会社として評価されたポイント
このプロジェクトで開発パートナーが高評価を得た理由は、単なる機能開発ではなく「業務の再設計」にまで踏み込んだ支援姿勢にあります。
- 実際のフィールド業務をヒアリングし、調整パターンや運用例をモデル化
- FirebaseやGoogle Maps APIを駆使し、予算内で実現性と拡張性を両立
- 通知・連携設計に柔軟性を持たせ、既存ツールとの併用も考慮
- 「現場業務にシステムを合わせる」思想でのUI/UX設計提案
このように、技術面と業務理解を融合させた提案力こそが、長期的な信頼に繋がると証明された事例です。
まとめ:現場調整をデジタル化することの意義
訪問型サービスにおける最大の非効率は、「スケジュールと移動の調整」です。紙・電話ベースの調整から脱却し、ルート・状況・スケジュールを「見える化」することは、単なる効率化ではなく、サービス価値そのものの再構築を意味します。
これから訪問業務支援システムを検討する企業にとっても、「スケジュール管理の範囲を超えた業務フロー設計」がカギになります。
受託開発会社としては、「現場がどう動いているか」を読み解き、業務設計と技術設計を重ね合わせて提案できる力が、今後のプロジェクト受注の競争力を決定づける要素となるでしょう。